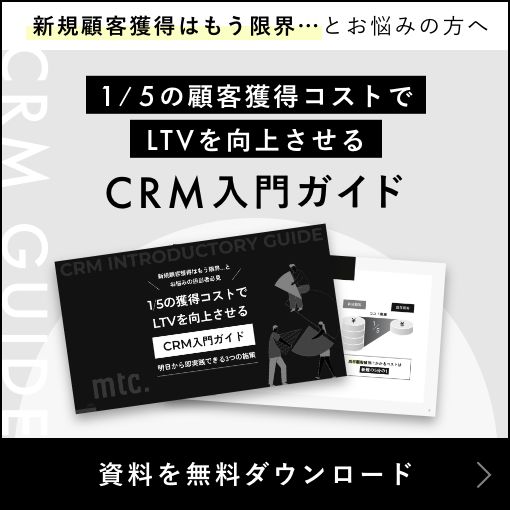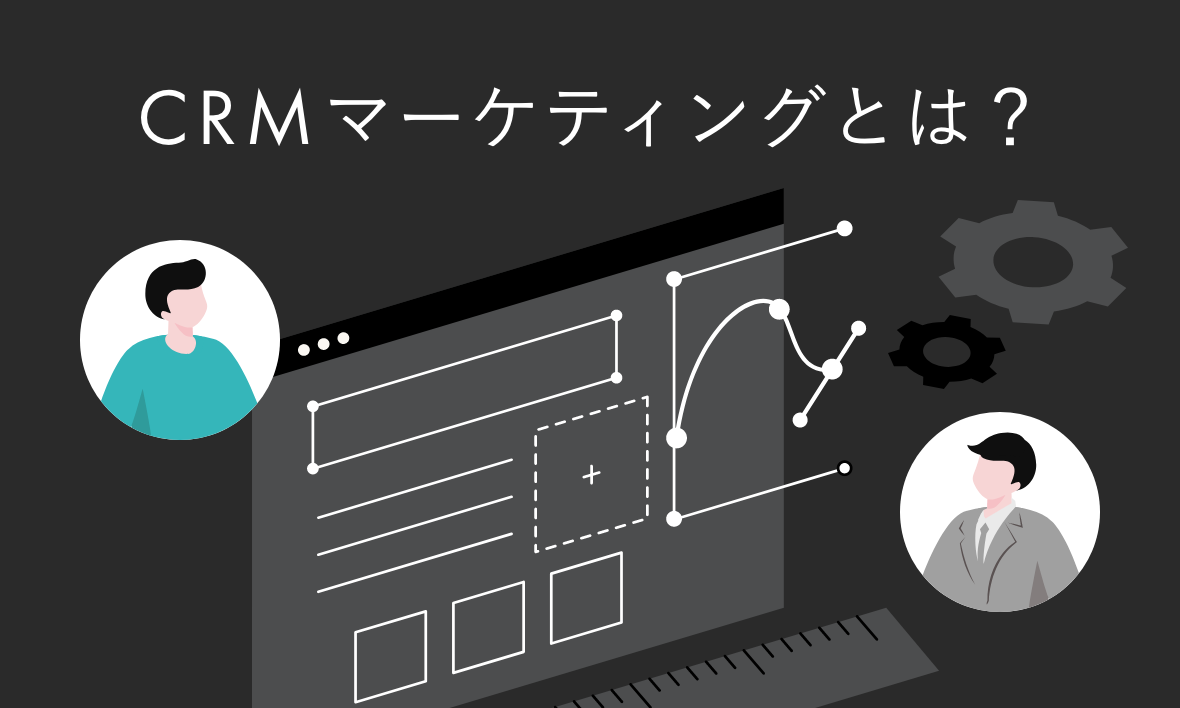化粧品業界のCRMが変える顧客体験─LTVとF2転換を伸ばす関係性設計の戦略とは
戦略プランナー
北村 健太

はじめに|売上を左右するのは「商品」ではなく「関係性」
化粧品業界では、ここ数年でEC化が一気に加速しました。店頭での接客が制限される中、オンラインを軸に顧客との関係を築いていく必要性が高まり、従来のマーケティング戦略ではカバーしきれない課題が顕在化しています。
こうした中で、多くの企業が気づき始めています。どんなに広告を出して新規顧客を獲得しても、その後の関係づくりに失敗すれば、顧客はすぐに離れてしまうということ。そして、いま売上を左右しているのは、商品の魅力だけではなく、そのブランドと顧客との間に築かれた関係性の質であるということです。
特に化粧品という商材は、機能だけで比較されるものではありません。肌との相性や香り、パッケージの世界観、ブランドがもたらす安心感など、感覚的で情緒的な要素が意思決定に大きく影響します。だからこそ、商品単体の訴求だけではなく、顧客がブランドと出会い、購入し、使い続けるまでの体験全体をどう設計するかが、これからのマーケティングにおける本質的なテーマとなっています。
その設計の中核を担うのがCRMです。CRMは単なるツールの導入や配信施策ではありません。顧客との関係を中長期で捉え、継続して選ばれるための関係構築を仕組みとして考える視点こそが、これからのCRMには求められています。
本記事では、化粧品業界におけるCRMの役割と考え方、そして顧客体験を起点にLTVを最大化するための具体的なアプローチや成功事例をご紹介します。関係をつくることが競争力となる今、CRMの再定義と実践に向けたヒントをお届けできれば幸いです。
01|CRMとは「関係性を設計する戦略」である
CRMという言葉は広く浸透していますが、その解釈は企業ごとにばらつきがあります。多くの現場では、CRMは「ツール導入」「メルマガ配信」「ポイント施策」など、施策や機能として語られがちです。しかし本質は、そうした手段ではなく「顧客との関係性をどう構築し、どう維持していくか」という戦略にあります。
CRMはツールの話ではない
CRMの本質は、「関係構築の仕組み化」です。目指すべきは、配信数や開封率といったKPIの達成ではなく、「このブランドは自分のことを分かってくれている」と顧客に感じてもらえる関係を、あらかじめ設計することです。
この考え方については、mtc.の別記事でも詳しく解説しています。CRMを「ツール導入」や「一斉配信」のような手段と切り分けて、ブランドとの関係性を育てる仕組みそのものとして再定義しています。
>関連記事:CRMとは何か?定義から考える“本質的なCRM”
顧客の状態は常に変化する
購入前と初回購入後では、顧客が感じている不安も期待も異なります。CRMではこの前提に立ち、顧客の態度や感情の変化に応じて、コミュニケーションを変化させていく設計が求められます。初回購入者に向けては不安を取り除くメッセージ、定着層に向けては共感や期待感を育てる体験設計など、フェーズごとに適切な関わり方があるはずです。
こうした設計がないまま「全員に同じタイミングで同じ内容を配信」してしまえば、顧客の関係性の質はむしろ悪化してしまいます。
顧客満足度とロイヤルティは別物
CRM設計においては、「満足してもらうこと」だけでは足りません。顧客が「また買いたい」「誰かに勧めたい」と思う状態をつくるには、ロイヤルティという視点が欠かせません。ロイヤルティは、感謝や納得、驚きといった感情を伴う体験の積み重ねによって醸成されます。
そのためには、単発的なキャンペーンやクーポンに頼るのではなく、ブランドとしての関係のあり方を社内で定義し、それを軸に一貫したコミュニケーションを設計していくことが必要です。
CRMは「管理」ではなく「構造設計」です。顧客の状態を見極め、関係性のあり方を企業として定義し、それに基づいた体験を提供し続ける。そのための戦略であり、仕組みがCRMなのです。
02|顧客体験が売上を育む 初回購入から2回目購入を分岐点とするCRM視点
顧客体験という言葉が多用されるようになった一方で、それを「サイトの使いやすさ」や「見た目のデザイン」の話にとどめてしまっているケースも少なくありません。mtc.が考える顧客体験とは、単なる接触の点ではなく、ブランドと顧客が築く関係の全体像として捉えるべきものです。
顧客体験は点ではなく、線で捉える
化粧品ECにおいて、体験は購入前から始まり、使用後の感想が形成されるまで続いていきます。商品詳細ページ、カート、配送、開封、使用、そして再購入に至るまで、それぞれの接点で顧客が何を感じ、どう記憶するか。そのすべてが「ブランドとの関係性」を形づくっています。
このような線上の体験を設計できていない場合、初回購入で得られた関心が自然と薄れていき、リピートにつながらないという問題が生じます。逆に言えば、体験を意図的に設計することで、継続購入へとつながる関係性を構築することができます。
なぜ2回目購入がLTVの最大分岐点になるのか
化粧品のようなリピート型商材において、2回目の購入は極めて重要です。初回購入はあくまで「お試し」段階に過ぎず、商品理解も使用実感もこれからという状態です。ここで適切なフォローや体験提供がなされなければ、「悪くはなかったけれど次は別のブランドを試そう」と考えられてしまいがちです。
mtc.が複数のD2Cブランド支援で得た知見でも、F2転換率がLTVの成長率に最も強く影響していることが明らかになっています。この2回目購入を後押しする仕組みをCRMで設計することこそ、事業の利益構造を根底から変える鍵になります。
ECと実店舗で異なる体験構造
実店舗では、スタッフの説明や雰囲気、接客などによって「関係の感覚」が自然と醸成されます。一方、ECでは顧客と直接会うことがなく、こうした感覚的な関係づくりが難しくなります。だからこそ、メールやLINE、同梱物といった無数の接点が、単なる情報伝達ではなく、ブランドとの関係性を育てる役割を担う必要があります。
CRMは、これらの接点を点在させるのではなく、「この顧客にとって、今このタイミングでこの内容を伝える理由」をきちんと設計し、つながりのある体験として届ける仕組みです。とくに初回購入後の不安や疑問、期待にどう応えるかは、CX設計において最重要のフェーズになります。
03|CRMによるCX強化の具体策 三つの視点でつくる顧客体験の設計
ここまで述べてきた通り、化粧品業界におけるCRMは、配信の最適化ではなく、顧客との関係構築そのものを支える戦略的な仕組みです。本章では、mtc.が現場支援で繰り返し実践してきたCRM設計の具体アプローチを三つの視点から紹介します。
1. 減点されない体験をつくる 期待を下回らないことを最優先に
化粧品というカテゴリは、使用感や香り、効果の実感といった主観的な評価軸が多く、期待値と実体験のギャップが離脱に直結します。そのため、プラスの驚きを演出する前に、まずはマイナスの印象を与えないことが重要です。
たとえば配送遅延の事前通知や、使用方法を丁寧に伝えるリーフレットの同梱など、基本的なコミュニケーション設計を徹底するだけで、体験の満足度は安定します。CRMは、このような「不満を生まない仕組み」から着手することで、継続的な関係づくりの土台を築くことができます。
2. フェーズごとの感情曲線に合わせた設計 判断の谷間を支える
顧客は常に一定のモチベーションを維持しているわけではありません。初回購入後の期待感、使い始めてからの戸惑い、効果実感前の不安など、フェーズごとに感情の波があります。mtc.ではこれを「感情曲線」として捉え、谷間のタイミングで適切な情報を届ける設計を行っています。
たとえば初回購入から一週間後に「よくある不安とその解消方法」を伝えるLINE配信を入れることで、離脱防止につなげた事例があります。逆に体験のピーク、つまり効果を実感しやすい時期には、継続購入や定期便の案内を行うことで、自然なアップセルにもつながります。
3. タッチポイントごとの役割を明確にする 同じメッセージを重ねない
顧客にとっての接点は、メール、LINE、商品同梱物、Web接客など多岐にわたります。ここで重要なのは、それぞれのタッチポイントに役割を持たせることです。たとえば、
- メール:じっくりと情報を伝える場所
- LINE:タイムリーな通知や感情への寄り添い
- 同梱物:購入直後の不安をケアし、期待を高める
- Web接客:瞬時に悩みを解決し、次の行動へ導く
このように、各タッチポイントが役割を分担し、顧客体験の中で矛盾や重複を起こさない設計を行うことで、一貫性のあるブランド体験が生まれます。
04|化粧品業界におけるCRMの活用事例 関係構築が成果に直結した4つのケース
ここからは、mtc.が実際に支援した化粧品ブランドの中で、CRMの思想と設計が顧客体験を大きく変えた事例を紹介します。成果を出すCRMとは、単なる配信の積み重ねではなく、関係性の構築そのものを支える設計思想であることが、これらの取り組みから見えてきます。
1. F2転換率が2倍に改善 実感ポイントに寄り添ったCRM設計
ある化粧品D2Cブランドでは、初回購入者の大半が2回目に進まず、F2転換率の低さがLTV向上のボトルネックになっていました。
mtc.はこの課題に対して、以下のようなCRM設計を導入しました。
- 顧客インサイトをもとに、初回購入後7日間の感情変化を仮説化
- LINEとメールでパーソナルな実感ポイントを伝える設計に変更
- 商品への期待を維持するコンテンツを同梱物で補完
結果として、F2転換率は短期間で2倍以上に改善。CRMが「不安を減らし、期待を維持する体験」を設計できた好例です。
>関連記事:初回購入からF2転換率が2倍に向上したCRM設計の事例
2. クーポン利用率が10倍に Web接客ツールによる文脈対応
別の化粧品ブランドでは、KARTEを導入していたものの、Web接客が定型的でCVに繋がっていませんでした。mtc.は文脈設計を見直し、接客ポップアップの出し分けや、ユーザー行動ごとの導線設計を実施。
- 商品詳細ページの滞在時間に応じて接客の出し方を調整
- 既存顧客には、過去購入商品に基づいた再提案を実施
- CV直前のタイミングで、限定クーポンを訴求
この取り組みにより、クーポン利用率が従来比で10倍に。CRMの思想がWeb接客にまで浸透し、ユーザー行動と接点が一致したことが成果につながりました。
>関連記事:CVRが1.2倍に改善したWeb接客シナリオの再設計
3. 継続出荷率が12パーセント改善 顧客の温度に応じた接点の再設計
継続購入を前提とする定期便モデルでは、「2回目から3回目」の定着フェーズが重要です。あるブランドでは、初回購入時の感動体験と2回目以降の接点設計にギャップがあり、リピート離脱が課題になっていました。
mtc.は以下のようなステップで改善を支援。
- 商品への感動体験を「言語化」するためのチェックシートを同梱
- 次回出荷前に、購入者のレビューや使い方投稿を紹介するLINE配信を実施
- 実感と信頼を育てるタッチポイントを再配置
結果、3回以上の出荷率が12パーセント改善。CRMによって感情と情報が接続され、ユーザーの意思決定を支える仕組みが定着しました。
4. EC売上が4年で約3倍に成長 土台から構築したCRMの全体戦略
ある化粧品メーカーでは、デジタルマーケティングそのものが未整備で、EC売上は伸び悩んでいました。mtc.は、CRMを中心に据えたブランド体験全体の設計を提案し、以下を支援。
- CRM戦略の立案と、社内での共通言語化
- 初回購入から定期リピートに至るCXマップの構築
- メルマガ、LINE、Web接客、アプリの役割分担を再設計
これらを実装する中で、EC売上は4年で約3倍に成長。CRMは単なるリテンション施策ではなく、マーケティング基盤そのものであることが体現された事例です。
05|CRMツールは「手段」である 選定と運用の正しい考え方
化粧品業界に限らず、CRM施策を進める上で「ツールを入れること」が目的化してしまうケースは少なくありません。しかし本来、CRMツールは戦略を実現するための手段であり、戦略・設計・運用体制と切り離されたまま導入しても効果は限定的です。
この章では、化粧品業界におけるCRMツール活用の考え方と、選定・運用の視点を整理します。
ツール導入は「やりたい施策が決まってから」が鉄則
ツール導入のタイミングでよく起こるのが「何ができるかを聞いてから施策を考える」流れです。しかし、この順序では施策が機能要件に依存してしまい、戦略的なCRMは実装できません。
本来あるべき流れは次の通りです。
- 顧客との理想的な関係性を定義する
- その関係構築のために必要な設計(CXマップ、シナリオ設計など)を行う
- 設計を実現するために必要な機能を洗い出す
- 必要条件を満たすツールを選ぶ
ツールは「やりたいことの再現性と拡張性」を担保するための存在であるべきです。
まずは手作業でテストし、効果を検証する
CRMの起点はツールではなく仮説です。特に化粧品業界のように、顧客の感情や使用実感に寄り添ったコミュニケーションが重要な領域では、仮説→実行→検証のループが欠かせません。
たとえば「F2転換率を上げたい」という仮説がある場合、
- 最初は手作業でメール文面をパーソナライズして送り、
- 効果が見えたタイミングで自動化・シナリオ化する
このような段階的な運用が、CRM設計と運用を社内に定着させる鍵になります。
化粧品業界で見るべきCRMツール選定のポイント
化粧品業界特有の文脈を踏まえた場合、以下のような観点でツールを見極める必要があります。
| セグメント自由度 | 商品ジャンル、肌悩み、購買回数、カウンセリング有無などで柔軟にセグメントが切れるか |
| チャネル統合性 | メール・LINE・Web・アプリなど複数接点を一元管理できるか |
| 実感のタイミング設計 | 出荷や到着など、CXに関わるトリガーを柔軟に設定できるか |
| 現場で運用しやすいか | UI、配信条件、分析機能などが複雑すぎないか |
| サポート体制 | 実装や改善提案を定常的に支援してくれるか |
これらはツールベンダーのスペック比較では見えづらいため、導入企業の事例を参照したり、トライアル期間で運用シナリオを組んでみることが効果的です。
化粧品CRMでよく使われる代表的なツール群
| KARTE | 行動ログ・感情ラベルなどをもとにWeb接客やLINE配信を細かく設計可能。toC商材での活用実績が多い。 |
| STAFF START | 店舗スタッフの接客力をデジタルに反映。化粧品業界ではカウンセリングやSNS連携活用が進んでいる。 |
| OTORIOKI(オトリオキ) | サブスク・定期便との親和性が高く、継続率改善の支援機能が豊富。顧客状態に応じた出し分けが可能。 |
なお、これらのツールに対しても「ツールありき」ではなく、戦略に基づく使い方が求められます。
06|CXを育てるCRM設計のために最初に着手すべきこと
CRMは顧客体験(CX)を育てるための設計図です。しかし、多くの企業が「何から手を付ければよいか分からない」という状態に陥りがちです。ここでは、CRMの設計において最初に整理すべき視点を紹介します。
顧客の状態を言語化する:態度状態の定義がすべての起点
施策設計に入る前に必要なのが、顧客の「態度状態」を定義することです。
たとえば、次のようなステップで状態を整理していきます。
- 認知前(ブランドを知らない)
- 興味喚起(SNSや広告で見たことがある)
- 比較検討(サイトを訪れて商品を見ている)
- 初回購入(購入しているが、まだ信頼には至っていない)
- 継続検討(商品体験を経て再購入を迷っている)
- ファン化(商品・ブランドに満足し、人に勧めたいと思っている)
これらの状態を社内で共通言語として持つことで、「今この施策は誰の、どの状態を変えようとしているのか」を明確にできます。
状態定義がないままでは、配信の打ち手がなんとなく良さそうなものの羅列になってしまい、継続的な改善が困難になります。
CXマップを「感情起点」で設計する:気持ちの動きを見る
態度状態の定義ができたら、次はそれに紐づく感情を想像します。
- 初回購入前は「不安」や「期待」が入り混じっている
- 購入直後は「ちゃんと届くか」「商品が合うか」という不安
- 使用後は「本当に効果があるのか」という疑念
- 2回目購入前は「この商品を続ける意味があるのか」と考えている
このように、感情の流れに沿って体験の設計をすることで、「次の一手」の文脈が自然に見えてきます。
CXとは、顧客がブランドに触れた瞬間瞬間でどう感じるかの積み重ねです。体験を点でなく線で捉える設計が、CRMの本質です。
接点の役割を整理する:タッチポイントは施策ではなく構造
メール、LINE、同梱物、Web接客、広告……それぞれの接点は、バラバラに運用されていませんか?
本来、接点ごとに担うべき役割があります。
- メールは「情報の整理と伝達」
- LINEは「親密さとタイムリーな接触」
- 同梱物は「購入体験の演出と記憶への定着」
- Web接客は「迷いの解消と即時の後押し」
それぞれが「誰の、どの感情にどう作用するのか」を設計することで、接点が構造として機能しはじめます。
お客様との関係性を「日本語ひと言」で定義する
最後におすすめしたいのが、「関係性の定義」を社内で共通化することです。
たとえば、
- このブランドは「悩んだときに相談できる存在」でいたい
- お客様にとって「味方のような存在」でいたい
- もっと言えば「日々のルーティンを応援してくれる存在」でありたい
このように、日本語でひと言にすることで、配信や接客のトーンや距離感も統一されていきます。
「誰にどう思われたいのか」を明文化することで、CRMは施策の積み重ねから、顧客との関係構築という一本のストーリーへと進化していきます。
まとめ:CRMは化粧品ビジネスにおける顧客との関係性を設計するための中枢
化粧品業界では、商品のスペックやプロモーションだけでは顧客の継続購入は生まれません。売上とLTVを決定づけるのは、「このブランドと付き合い続けたい」と思ってもらえるかどうかという、関係性の質です。
その関係性を仕組みとして育てていく視点こそが、CRMの本質です。特に以下の3点が重要です。
- 顧客体験を点ではなく線で設計すること
- 顧客の感情や態度変容を基軸にコミュニケーションを構築すること
- 施策を打つ前に、「誰とどんな関係を築きたいのか」を明文化すること
CRMはツールでもテクニックでもありません。戦略、体験設計、組織全体の意志をひとつに束ねる、事業成長の骨格そのものです。
ブランドと顧客が、もっと信頼し合える関係を築く。その起点として、改めて「CRM設計」を見直してみてはいかがでしょうか。マーケティングの文脈にとどまらず、事業全体を貫く共通言語としてのCRMを、私たちはこれからも追求していきます。
ご相談はこちら
mtc.では、化粧品業界向けにCRM構造診断を無料で実施しています。
今のCRM施策は、誰の、どのフェーズを対象にしているのか?
- 顧客の気持ちの動きに合わせたCX設計になっているか?
- ツールに振り回されず、感情ベースでの関係設計ができているか?
といった視点から、「売上を生むCRMの構造」を一緒に見直し、具体的な改善のヒントをご提供します。