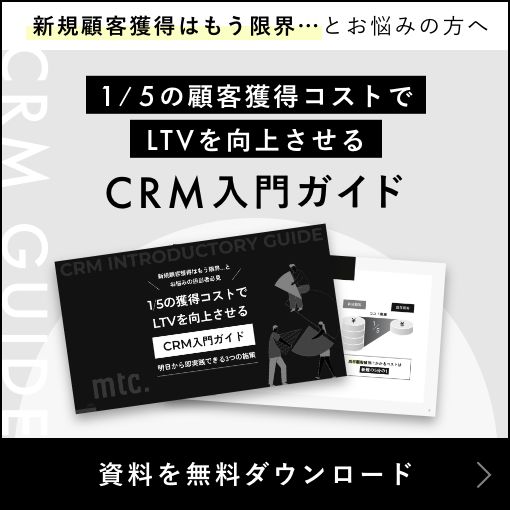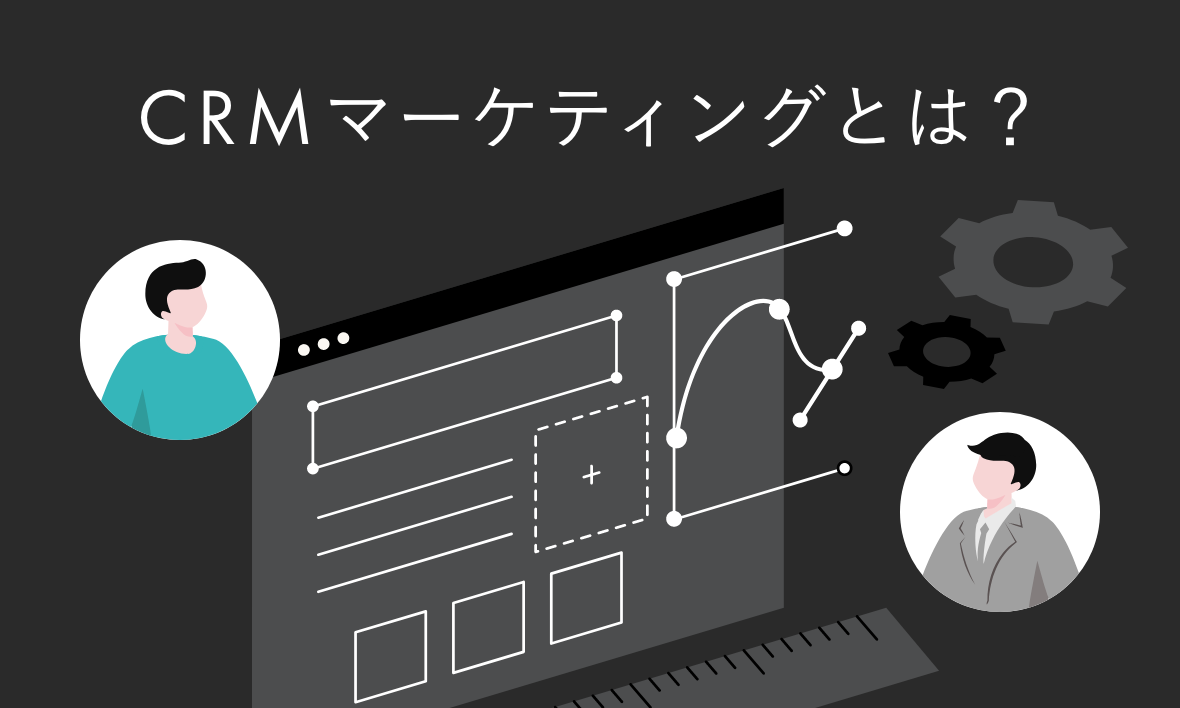CRMにおけるカスタマージャーニーとは?
戦略プランナー
北村 健太

関係性の変化を設計する“状態遷移の構造”の描き方
01|カスタマージャーニーとは何か?──「状態遷移を支える構造」としての再定義
一般的に、カスタマージャーニーは「顧客が商品やサービスと出会い、購入・継続利用に至るまでのプロセス」として描かれます。多くの場合、それは「認知→興味→比較→購入→利用」といった線形モデルです。
しかし、mtc.のCRM思想におけるジャーニーは、そのような購買行動の段階ではありません。
mtc.では、カスタマージャーニーを「顧客の状態(態度)の変化を支える構造設計」と定義しています。
たとえば、
- 「知ってはいるが、まだ自分ごとになっていない」
- 「気になっているけれど、試す理由が見つからない」
- 「使ってはいるが、本当に続けるかは迷っている」
といった“心の状態”ごとに、関係性を分解し、設計する必要があるのです。
02|なぜCRMにおいて“態度変容の地図”が必要なのか
CRM施策はしばしば「チャネル最適化」や「セグメント配信の精度」ばかりに意識が向きがちです。しかし、それだけでは顧客との関係性は深まりません。
なぜなら、顧客が前に進まないのは“情報が足りないから”ではなく、“納得や確信が未熟だから”です。
顧客の状態とは、気温のように“グラデーション”で変化していくもの。その変化に合わせた設計を行わなければ、CRM施策は行き届かず、成果にもつながりません。
03|ジャーニー設計の5ステップ(mtc.式)
1|関係性フェーズの分解(状態遷移を洗い出す)
- 認知・検討・購入といった購買段階ではなく、「信じているか」「不安を感じているか」「理由を持っているか」といった“態度レベル”のフェーズ分解
2|各状態における“停滞理由”の分析
- 顧客はなぜ次に進まないのか?
- 例:「初回購入したが、継続理由が見つからない」「比較しているが、違いがわからない」など
3|チャネル別“役割”の再定義
- LINE=温度を上げる/メルマガ=納得を支える/同梱物=期待に応える など
- 接点ごとに「どの状態を動かすか」を定義することが重要
4|態度変容KPIの設定
- 「開封率」「CVR」ではなく、「商品理解率」「納得層の割合」「試用継続率」など
- 顧客の“心の位置”に基づく変化を測る指標を設計する
5|状態起点で配信シナリオを組む(タイミングとトリガー)
- 例:「比較層に対して、商品比較のストーリーを届ける」「迷っている層に“後押しの理由”を届ける」
04|カスタマージャーニーを制作するプロセスとは?
実際に、状態遷移のジャーニーをどのように描いていくのか。mtc.が現場で用いている、シンプルかつ実践的なプロセスは以下の通りです。
STEP 1|顧客とブランドの関係性を「動詞」で捉える
- 「知る」「気になる」「比べる」「納得する」「買ってみる」「続けて使う」など、顧客が起こす行動・心理変化を動詞で洗い出します。
STEP 2|その動詞ごとの“阻害要因”を可視化する
- なぜ「比べている」で止まってしまうのか?
- なぜ「知っている」けど「気にならない」のか?
- 背景にある不安・知識不足・決め手不足を列挙
STEP 3|阻害要因に対して「状態を変える接点」をマッピング
- メール、LINE、同梱、WEB接客、CSなど、変化を促せる接点を洗い出します
- 接点の「役割」を定義(例:メール=納得支援、LINE=温度引き上げ)
STEP 4|ジャーニーマップを“状態遷移 × 接点”の行列で描く
- 横軸に「状態の変化」、縦軸に「接点の役割とトリガー」
- KPIやクリエイティブの粒度を入れていく
STEP 5|“動かせていない状態”を明確化し、優先順位を定める
- どのフェーズに“滞留”している人が多いか?
- その状態の人を動かすには、どの接点が未整備か?
このように、ジャーニー制作は「情報を並べること」ではなく、「どの状態を、どの接点で、どう動かすか」を設計していくプロセスです。
05|よくある失敗とその構造
失敗①:「F1→F2」などの購買単位で分けてしまう
→ 顧客の“心の状態”は購買回数では定義できない。継続していても迷っている人もいれば、初回でも信じている人もいる。
失敗②:接点の役割があいまいで、情報提供に終始する
→ 「何を届けるか」ばかりにフォーカスし、「なぜ届けるか(どの状態を動かすか)」が抜けている
失敗③:KPIがチャネル都合で設計されている
→ LINEの開封率やメルマガのCTRなど、個別の成果は見えても“全体の関係性進行”が見えない
06|事例で読み解く:関係性を設計したジャーニーが成果に変わった例
● F2転換率が2倍超に改善したD2Cブランド(化粧品EC)
- 顧客の「効果が実感できなければ次はない」という状態を定義
- 「実感の兆し」を届けるCRMメール設計に刷新
- 不安を抱えていた状態を「信じてみる」に変化させた結果、F2転換率2倍超に
→ 事例を見る
● 比較層向けCVR改善施策(ECサイト×KARTE)
- 商品詳細ページ閲覧後の“決め手が見つからない”状態に注目
- 接客ツールと連動したメールで「他の人の選定理由」を提示
- “比較中”から“納得して選ぶ”への変化を促進
→ 事例を見る
07|まとめ:CRMとは、状態を分けて、変化を促す構造を描く営みである
- カスタマージャーニーは、接点の流れではなく、「関係性を深めるための構造設計図」
- 顧客の“心の状態”を正しく理解し、その状態ごとに設計することが、CRMの要諦
- 状態を定義し、接点の役割を分け、チーム全体で“状態を動かすCRM”を共通認識にする
mtc.では「CRM構造診断(カスタマージャーニー編)」を無料で提供中。
- 顧客の態度変容に応じた設計ができているか?
- 今、もっとも動かすべき“状態”はどこか?
- 接点が本当に“状態を変える役割”を果たしているか?
無料相談から、CRMの再設計を一緒に始めてみませんか?