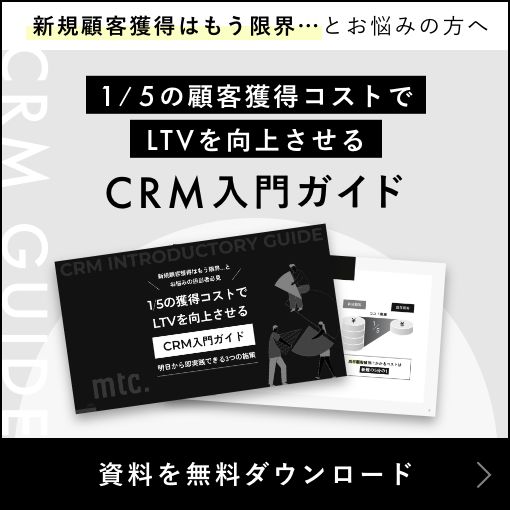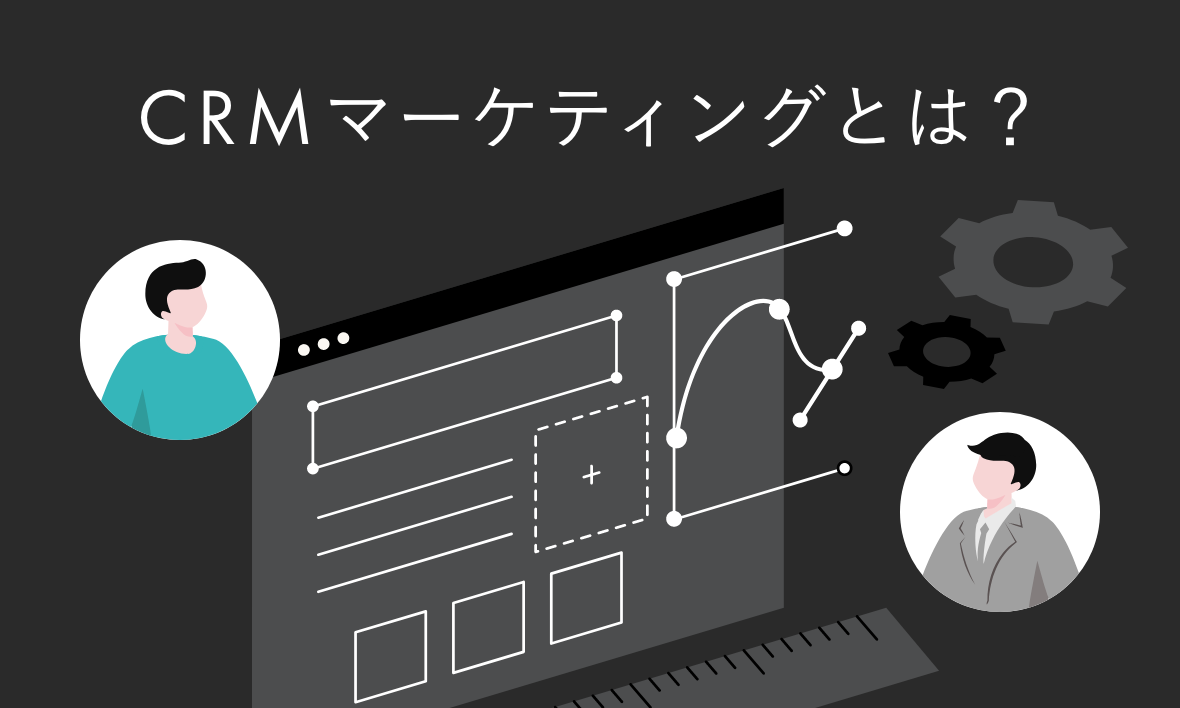休眠顧客に響くCRMとは。関係性の再構築で再購入につなげる戦略と実践
戦略プランナー
北村 健太

はじめに|CRMは終わった関係を再びつなぐ手段になり得るか
新規獲得に注力してきた事業者ほど、ある段階で「休眠顧客の多さ」に直面します。広告でせっかく獲得したのに、購入が一回で終わる。定期商品を一度試して終わる。アクセスが止まり、音沙汰がなくなる。このような「終わってしまった関係」が、データベースの大半を占めるようになっているケースも珍しくありません。
休眠顧客施策は、いわばCRMの中でも「関係性の再設計」という特殊な領域です。既存のシナリオが届かない相手に対し、どんなタイミングで、どんな文脈で、どんな体験を届ければ、もう一度こちらを振り向いてもらえるのか。そこには、通常のLTV施策や定期継続支援とは異なる論点と工夫が求められます。
この記事では、mtcがこれまでに実践してきたCRM支援の知見をもとに、休眠顧客に対する向き合い方と、関係を取り戻すための設計論について解説していきます。
今のCRMは、離れていった顧客の「気持ち」を、きちんと見ているか。
届けたいのは情報ではなく、もう一度つながりたいという意思です。
そのために必要な考え方と構造を、順を追ってお伝えしていきます。
01|なぜ休眠顧客が生まれるのか。その構造を見直す
休眠顧客は、単なる「再アプローチすべき対象」ではありません。
そもそもなぜ休眠に至ったのかという原因を見極めなければ、どれだけ訴求を重ねても関係性は再生しません。
● 原因の多くは「期待と現実のギャップ」
顧客が一度は商品を購入したという事実は、一定の期待や関心があったことを意味します。
しかし、その後に続かなかったということは、以下のようなズレが生じていた可能性があります。
- 商品の実感や効果が想定と違った
- サービス体験がストレスだった
- 商品を使いこなせなかった
- そもそも「続ける理由」がわからなかった
これらのギャップは、商品のスペックだけでなく、情報設計や体験導線にも大きく影響されます。
言い換えれば、休眠化は「購入後の体験設計ミス」として捉えるべきです。
● 休眠は失敗ではなく、体験の未完了である
重要なのは、休眠という状態を「見込みがない」と切り捨てないことです。
むしろ、関係性が一度あったからこそ、適切な接点と文脈があれば、再び購入やファン化につながる可能性が高いとも言えます。
特にサブスクリプション型のサービスや、使用継続が前提の商品を扱う事業では、
初回購入以降の顧客フォローが弱いほど、休眠率は高くなる傾向があります。
CRMが果たすべき役割は、「購入された後」の感情や行動を観察し、
離脱が起きる理由を構造的に潰していくことにあります。
● 休眠化のタイミングは商品によって異なる
もう一つ押さえるべきポイントは、休眠化が起きるタイミングが商材ごとに異なるということです。
- 健康食品であれば、初回購入から二回目までのスパン
- 化粧品であれば、使用開始から実感が生まれるまでの期間
- サービス系であれば、利用体験が一巡する前後
このように、商品特性と顧客の使用行動を照らし合わせて、
「どの瞬間に失望や無関心が生まれているのか」を把握することが、休眠施策の起点となります。
02|休眠顧客施策でよくある間違い
休眠顧客へのアプローチは、多くの企業が取り組んでいるCRM施策の一つです。
しかし、その多くが成果につながっていないのが実情です。原因は、アプローチの構造設計が不十分なまま、施策だけが独立して存在していることにあります。
● 一斉配信で「掘り起こし」を狙う失敗
「久しぶりにご案内です」「またご利用ください」といったメッセージを一斉に送る。
こうした配信は、受け取る側にとっては急に連絡してきた都合のいいブランドに見えるリスクがあります。
文脈も前提も共有されていないまま、プロモーションだけが届く。
これは一方的なセールスに過ぎず、再エンゲージメントにはつながりません。
● 「買ってください」ではなく「思い出してください」
休眠顧客への第一歩は、購入を迫ることではありません。
まずは、かつて自分がそのブランドに興味を持っていたこと、商品を選んだ理由、その時の感情を思い出してもらうことが重要です。
- なぜこの商品を選んだのか
- どんな期待があったのか
- 使ってどう感じたのか
これらを思い出してもらうことで、顧客側に「再びつながる意味」が生まれます。
その文脈を提示しないまま配信を続けても、離脱率がさらに高まるだけです。
● 「オファーを強くすれば売れる」の誤解
割引クーポンやポイント還元など、オファーを強くすることで再購入を狙う施策も多く見られます。
確かに短期的な売上にはつながるかもしれませんが、これは「価格を下げないと買わない顧客」を育てる結果にもなりかねません。
本来の目的は、再びブランドと自発的につながりたくなる顧客を育てること。
オファーはその補助に過ぎず、中心に据えるべきものではありません。
03|関係を再構築するためのステップ設計
休眠顧客を呼び戻すというよりも、改めてつながり直す。
この視点に立ったとき、単発のキャンペーンや一度限りの特典ではなく、段階的に関係性を再構築していくステップ設計が求められます。
● ステップ1:思い出してもらう
最初の接点では、今すぐ再購入を促すのではなく、過去にブランドと接点を持っていた時の記憶や体験を想起してもらうことが目的になります。
たとえば、次のような設計が有効です。
- 以前に購入した商品の使用シーンを思い出させる
- 初回購入時の期待感や満足感を再確認してもらう
- 他ユーザーの体験やレビューを通じて共感を引き出す
このステップでは、ブランドに対するポジティブな記憶の再生が鍵となります。
● ステップ2:つながる意味をつくる
思い出してもらった後は、なぜ今また関係を持つべきなのか、その理由を丁寧に提示します。ここでは、商品やブランドの変化だけでなく、顧客の生活変化に寄り添ったアプローチが重要です。
- 季節やライフスタイルの変化に応じた商品提案
- サービス内容やラインナップのアップデート情報
- これまでとの違いや新たな価値を伝えるコンテンツ設計
この段階では、売り込みではなく、今つながる意義を提示することで、自然な関係の再接続を目指します。
● ステップ3:購入への納得感をつくる
再度ブランドに関心を持ってもらったとしても、行動に移すには「なぜ今これを選ぶのか」という明確な納得感が必要です。
ここでの設計ポイントは以下の通りです。
- 顧客の現在のニーズに即した提案にする
- 価格訴求よりも、再購入の理由やメリットを丁寧に言語化する
- 小さなアクション(レビュー閲覧やチェックシート)を挟み、心理的ハードルを下げる
購入という結果だけをゴールにせず、納得して選んでもらうプロセスをつくることが、長期的な関係構築につながります。
04|休眠復活で成果を出すためのCX設計
単にメールやクーポンを送るだけでは、顧客は戻ってきません。
顧客の記憶と感情に働きかけ、ブランドとの関係をもう一度築き直すには、顧客体験そのものを再設計する必要があります。
● 顧客の心理と行動変容を前提とした設計
休眠状態にある顧客は、かつては購入や利用の意思があったものの、何らかの理由でブランドとの関係が止まっています。
この「離れてしまった理由」は、必ずしもネガティブとは限りません。
たとえば以下のようなケースがあります。
- 商品の役割が一時的に終わった
- 忙しくてリピートのタイミングを逃した
- 他社を試している最中だった
- 体調や生活環境が変化して一度離れた
これらの状態にある顧客に対しては、単に再購入を求めるのではなく、
「今の自分に必要だ」と再認識してもらう体験が求められます。
● CX設計のポイント1:接点の目的を明確にする
再接続を目指す全ての接点において、「何のための接点か」が設計されていないと、顧客にとっては意味を持たないコミュニケーションになります。
- メールなら、文脈の再接続や現在の価値提供の提示
- LINEなら、ライトな再関与の入り口や情報収集の場
- サイト上のポップアップなら、タイミングと内容に意味のある提示
接点ごとの目的が整理されていれば、顧客が無理なく再接続できる体験が生まれます。
● CX設計のポイント2:体験の流れを線で設計する
休眠復活は、単発の施策で実現するものではありません。
- 思い出す
- 関心を持つ
- 必要性を感じる
- 行動する
このようなプロセスを想定し、接点や施策を連動させていく必要があります。
例としては以下のようなステップ設計が考えられます。
- 初回接点での記憶想起(レビュー、体験談、購入履歴)
- 次の配信での現在価値の提示(新商品、使い方の提案、事例)
- 軽いアクションを促す(LINE登録、チェックシート回答)
- 最後に再購入訴求(限定オファー、カートリマインド)
このように、顧客の感情や行動に沿った「線」で設計された体験が、再購入や再利用の確率を高めます。
● CX設計のポイント3:行動の変化を指標で追う
配信数や開封率ではなく、「どの接点が再購入につながったか」「どの体験がアクションのきっかけになったか」を見極めることで、CX設計の解像度が上がります。
- 記憶想起系コンテンツのクリック率
- 行動トリガーの直後のコンバージョン
- 再購入後の継続率やレビュー投稿率
こうした指標を通じて、感覚ではなく事実ベースでCXの改善が可能になります。
05|CRMによる休眠復活の事例紹介
休眠顧客へのアプローチは、CRMの中でも成果が見えやすい領域のひとつです。特に、感情が途切れてしまった顧客との再接続には、接点の出し方だけでなく、文脈やタイミングの設計が重要になります。ここでは、mtc.が支援したあるD2Cブランドでの取り組みを紹介します。
● 新商品発売を契機に休眠顧客へ再アプローチ
あるD2Cブランドでは、新商品発売のタイミングに合わせて、過去に商品を購入したものの一定期間離脱していた休眠顧客層に対し、再接点を設計しました。
単に「休眠顧客一斉配信」ではなく、休眠状態の深さや興味関心の違いを踏まえたセグメンテーションを実施。具体的には、以下のようなデータに基づく分類を行いました。
- 最終購入日(例:3ヶ月〜6ヶ月、6ヶ月以上など)
- 購入した商品カテゴリや価格帯
- 購入回数や過去の配信反応履歴
これらの条件から細分化したターゲットに対し、新商品の魅力が過去購入体験とつながるような文脈でメッセージを設計。メール、LINE、同梱物などチャネルごとに役割を持たせ、複数の接点を用いてリマインドを行いました。
● 休眠復活数は5000人超え
この取り組みにより、休眠状態から復活し再購入につながった顧客は5000人以上にのぼりました。
単なる「割引訴求」や「限定キャンペーン」ではなく、過去の体験を軸にした再提案が功を奏した形です。
さらに、復活後のLTVは全体平均よりも高く、関係性を一度築いた顧客は再度つながると強いロイヤル層になりやすいという仮説も実証されました。
06|休眠顧客アプローチを成功させるために最初に着手すべきこと
休眠施策は、「久しぶりの接点」になるからこそ、緻密な準備が必要です。ただ配信をすれば成果が出るわけではなく、なぜ離れたのか、なぜいま届けるのかを論理と感情の両面で整理する必要があります。以下に、休眠顧客アプローチを設計する上で、最初に着手すべきポイントを整理します。
● 顧客の「離反要因」を見極める
まず大切なのは、「なぜ顧客が離れたのか」の仮説を立てることです。価格なのか、使用感なのか、そもそも効果実感がなかったのか。購入体験のどこにギャップがあったのかを洗い出すことで、再接点で何を届けるべきかが見えてきます。
データとしては以下のような項目が活用できます。
- 最終購入商品と使用想定期間の乖離
- お問い合わせ履歴や返品理由
- 開封率やサイト訪問頻度の推移
● 休眠の「定義」と「深度」を決める
CRM施策で成果を出すには、誰を休眠とみなすかの定義が重要です。単に「3ヶ月未購入」だけでなく、商品カテゴリ・購入頻度・顧客の態度状態を含めて、休眠の深度を多層的に見る必要があります。
例:
- 購入1回のみ・6ヶ月未購入:初期離反層
- 購入2回以上・12ヶ月未購入:ロイヤル層からの離反
- 過去高LTV・現在無反応:感情的距離が広がった可能性あり
こうした定義があることで、配信の粒度も自然と変わります。
● 「いま届ける理由」を文脈で設計する
休眠復活のアプローチは、再購入を「促す」のではなく、「納得できるきっかけ」をつくることが本質です。
そのためには、以下のような「文脈接続」が効果的です。
- 新商品発売 → 過去購入商品の後継性・相性の訴求
- 季節や悩みの変化 → 一度離れた顧客にとって気になる理由を設計
- ブランドの進化 → 「前と同じではない」という変化を伝える
顧客の気持ちの中に再びこのブランドに触れる理由を生み出すことが、休眠復活の第一歩になります。
● 「誰が・どこで・どんな役割で」伝えるかを整理する
最後に、接点とチャネルの使い方を構造化しておくことが大切です。メール・LINE・同梱物・SNSなど、チャネルごとに役割を持たせ、「誰に何を伝えるのか」を設計に落とし込みます。
例:
- メール:データベース全体への通知や新商品案内
- LINE:距離が近いユーザーへの限定情報やリマインド
- 同梱物:復活後の体験向上のためのエモーショナル訴求
これにより、「伝えるべきことを、最も効果的なチャネルで」届ける構造が実現できます。
まとめ|CRMは休眠顧客との「再関係構築」の設計図である
休眠顧客施策は、一度関係が途切れた相手ともう一度向き合う、非常に繊細なマーケティング活動です。ただ情報を届けるのではなく、「なぜまたこのブランドとつながる意味があるのか」を納得してもらうことが、復活の鍵になります。
そのためには、休眠の要因を見立て、再接点の文脈を設計し、接点の役割まで丁寧に構築していく必要があります。CRMは、このプロセスを一過性の施策ではなく、仕組みとして再現するための戦略設計図です。
mtc.では、配信ではなく「関係性そのものの構造設計」を通じて、ブランドのLTV最大化を支援しています。
ご相談はこちら
mtc.では、化粧品業界向けにCRM構造診断を無料で実施しています。
- 今のCRM施策は、誰の、どのフェーズを対象にしているのか?
- 顧客の気持ちの動きに合わせたCX設計になっているか?
- ツールに振り回されず、感情ベースでの関係設計ができているか?
といった視点から、「売上を生むCRMの構造」を一緒に見直し、具体的な改善のヒントをご提供します。