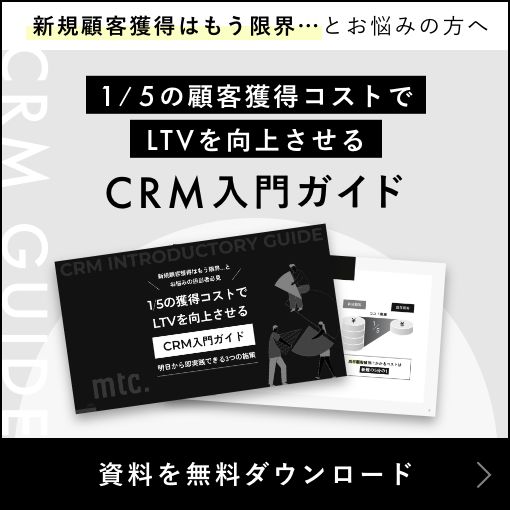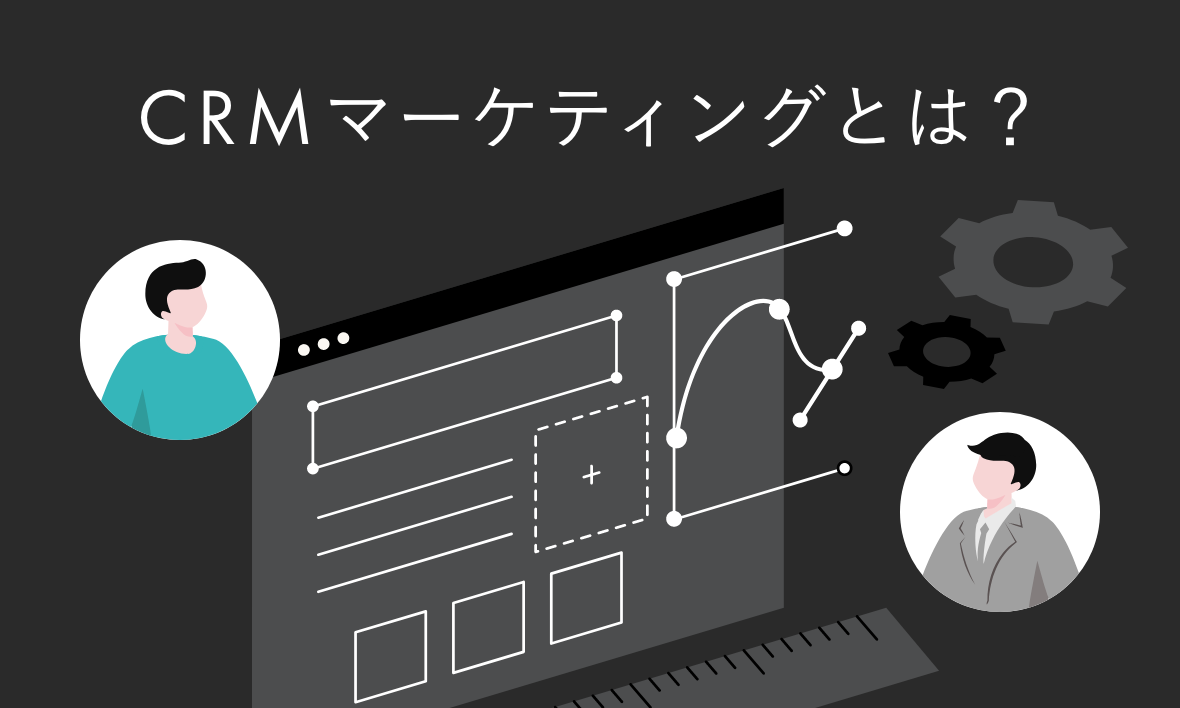D2CにおけるCRM戦略とは何か。継続率を高める関係設計の全体像
戦略プランナー
北村 健太

はじめに|D2Cにおける成長の壁は「続けてもらう仕組み」にある
D2Cというモデルは、仲介を挟まず自社で顧客とつながれる強みを持ちながらも、成長が鈍化するタイミングがあります。それは「新規は取れているのに、継続が続かない」という壁に直面したときです。
広告やSNSを活用して一定数の初回購入を得られていても、継続購入に繋がらなければLTVは伸びず、マーケティング投資の回収も不安定になります。加えて、D2Cでは顧客との接点がデジタルに限られ、店舗のような空間や接客に頼れない分、購入前後の体験が関係性を大きく左右します。
そこで必要なのが、CRMの視点です。ただし、ここで言うCRMとは、配信ツールや自動化シナリオのことではありません。D2Cブランドにとって本当に必要なのは、「顧客とどんな関係を築きたいか」を起点に、データ・チャネル・タイミングを設計し、継続につながる関係性を再現可能な仕組みに落とし込むことです。
本記事では、D2C事業におけるCRMの本質を再定義し、継続率を高める関係設計の全体像を提示します。成功しているD2Cブランドが実践している戦略や構造、そして成果を出すための具体的なアプローチまでを、順を追って解説していきます。
01|D2CモデルにおけるCRMの役割とは何か
D2Cブランドの本質的な強みは、自社が顧客と直接つながれる構造にあります。仲介を介さずにデータを保有し、顧客理解を深めることができる点で、大手小売やモール型ECと差別化が可能です。しかし、その強みを最大限に活かすためには、ただの販売管理ではない「顧客関係設計」が求められます
◯継続率こそが事業の未来を左右する
D2C事業において最大の課題は「初回購入後の継続率」です。広告による集客やSNSによる認知はある程度スケールしますが、リピートにつながらなければ事業は安定しません。
特にF2、つまり2回目の購入は、LTVを左右する最大の分岐点です。初回購入で終わる顧客をどれだけ次につなげられるかが、マーケティングROIに直結します。ここで必要なのが、CRMの視点です。
◯CRMは「施策」ではなく「設計」
CRMというと、多くの企業が「メールを送る」「LINEを配信する」といった施策レベルで捉えがちです。しかし、mtc.ではCRMを「顧客との関係性を再現可能な構造として設計すること」と定義しています。
この構造設計には、以下のような視点が必要です。
- 顧客の状態を段階的に把握し、適切なタイミングで関係性を深めていく
- 接点ごとの役割を明確にし、チャネルを横断した一貫性ある体験を設計する
- 誰に、なぜ、いまこのコミュニケーションを届けるのかという文脈をもとに、施策を運用する
CRMは顧客データをもとに「続けてもらう関係性」をデザインすることに他なりません。
02|初回購入からF2転換までがCRMの勝負所
D2C事業におけるCRMの最重要フェーズは、初回購入からF2、つまり2回目の購入までの期間です。この短い期間こそ、顧客との関係性が急速に深まりもすれば、簡単に途切れてしまう局面でもあります
● なぜF2が重要なのか
初回購入の時点では、顧客はまだブランドに対して「興味」や「期待」を抱いている段階にすぎません。ここで体験が良ければ継続に進みますが、期待を下回ったり、放置されたりすれば離脱につながります。
このF2転換の成否が、LTV(顧客生涯価値)やリピート率を大きく左右するため、mtc.ではこのフェーズをCRM施策の最重要ポイントとして位置づけています。
● 初回購入直後は「態度変容」がもっとも起きやすいタイミング
初回購入後の数日間は、顧客の期待がもっとも高まっているタイミングです。この時期に、ブランドからの適切なコミュニケーションがあるかどうかで、次のアクションへの心理的ハードルは大きく変わります。
具体的には以下のような状態変化が生まれやすくなります。
- 購入直後の「期待状態」から、「使用後の実感」への変化
- 商品やブランドへの「信頼の芽生え」
- 次回購入への心理的ハードルの低下
このような変化に対してタイムリーにアプローチするためには、CRMを構造として捉える視点が欠かせません。
● mtc.が重視する「感情起点」のCRM設計
mtc.では、F2転換のための設計を「顧客の感情曲線」に沿って設計することを推奨しています。例えば以下のようなシナリオです。
- 商品到着から3日後に、「使用感はいかがですか?」という内容のLINE
- 商品の使用法や効果実感ポイントを伝えるパーソナライズドなメール
- 開封率だけでなく「読む意味がある」同梱物設計
これらはすべて、顧客の「判断の谷間」に寄り添う関係性設計です。
このように、初回購入後の数日間でいかに関係性を深められるかが、その後の継続・ファン化を左右します。
03|D2CのCRM設計における3つの視点
D2Cビジネスにおいて、CRMを単なる施策や配信の集まりとして捉えると、効果は限定的になります。重要なのは、「誰に、どのタイミングで、何を伝えるべきか」という構造を持った関係設計です。ここでは、mtc.が重視する3つの視点から、CRM戦略の設計アプローチを紹介します。
1. フェーズ設計:顧客の状態を軸にしたコミュニケーション設計
まずは、顧客の状態を適切に分解することから始まります。
- 新規(初回購入前)
- 初回購入直後(期待が高まっている)
- リピート促進期(F2〜F3)
- 定着顧客(購買が安定している)
- 離反予備軍(購入がしばらくない)
これらのフェーズを明確に定義することで、各フェーズに対して必要な情報・タイミング・チャネルを整理することができます。
CRMが機能しない企業の多くは、「誰に対して」「何を目的に」施策を実施しているのかが曖昧なまま運用されており、施策が一貫性を持ちません。フェーズ設計は、この一貫性の土台をつくる作業です。
2. 態度変容ベースのセグメント設計
D2Cでは、購買履歴だけでなく、行動データや心理状態も含めたセグメント設計が重要です。
たとえば、以下のような切り口でのセグメント分解が考えられます。
- メールは開くがクリックしない
- LINE経由での購入が多い
- カート投入後の離脱が多い
- レビュー投稿やSNSシェア経験あり
こうした「態度変容」に着目することで、単なる属性ベースでは見落としてしまう微細な状態変化に対応したアプローチが可能になります。
3. タッチポイントの役割設計
タッチポイントごとに、何を支えるかを定義することも不可欠です。
- メール:定期的な安心感やブランドの思想を伝える
- LINE:即時性や限定感のある施策に活用
- 同梱物:商品に触れる瞬間に、ブランド体験を訴求
- Web:接客体験やQ&Aで不安の解消
これらを明確に位置づけておくことで、顧客がどこで迷い、どこで納得し、どこで感動するかを計算に入れた構造的なCRMが可能になります。
04|D2CビジネスにおけるCRM活用の成功事例
D2C(Direct to Consumer)モデルでは、広告や卸に依存しない分、顧客と直接関係を築くCRMの精度が売上の継続性を左右します。この章では、実際にCRMを戦略的に活用し、成果を上げたD2Cブランドの事例を紹介します。
● 顧客インサイトから設計したコミュニケーションでF2転換率が2倍に
ある化粧品系D2Cブランドでは、初回購入後の2回目購入(F2)への転換が課題でした。購入体験に対する実感を得る前に離脱してしまうケースが多く、LTVが伸び悩んでいたのです。
mtc.ではこのブランドに対し、F2転換を阻害している要因を顧客インサイトから洗い出し、「初回体験後の感情の変化」を軸にコミュニケーションを再設計しました。
- 初回購入から7日以内に、悩みや期待に応じたLINEとメールを配信
- 同梱物と連携した体験導線の最適化
- 顧客の不安を取り除くQ&Aや使用実感を後押しするレビュー情報の届け方を改善
この結果、F2転換率は短期間で2倍以上に改善。CRMを施策単体ではなく「顧客体験の流れ」として設計したことが成果につながりました。
● 新商品発売時に休眠顧客へアプローチし、5000人以上を再活性化
別のD2Cブランドでは、新商品発売のタイミングを活用して、過去に一定の購入履歴がありながらも離脱していた休眠顧客層へ再アプローチを行いました。
この施策では、休眠顧客を以下のようにセグメンテーションした上で、アプローチを最適化しました。
- 最終出荷日(離脱時期)の近さで分類(直近3ヶ月・6ヶ月・1年以上)
- 購入カテゴリごとの興味関心別分類
- 買い切り型か定期型かの購入スタイルで分類
各セグメントに対して、新商品の魅力をパーソナライズして伝えるメールとLINE配信を行った結果、5000人以上の休眠顧客が再購入につながりました。
新商品というきっかけを活かしつつ、関係の文脈を分けて設計することで、ただのキャンペーンではなく、CRM文脈での休眠復活を実現した好例です。
05|D2CのCRMで見落とされがちな落とし穴
CRMの設計や運用において、理論や成功事例に基づいた取り組みは重要ですが、実際のD2C現場ではいくつかの落とし穴に陥りやすい構造があります。ここでは、よくある3つのつまずきポイントを整理します。
● 配信数だけをKPIにしてしまう
D2C事業の多くが陥るのが、メールやLINEなどの配信件数そのものを評価指標にしてしまうケースです。配信数が増えていても、それが顧客の行動変容につながっていなければ意味がありません。
重要なのは、誰に、いつ、どんな目的で届けたか。その結果、何が変わったかをKPIとして設計することです。クリック率や開封率も参考になりますが、F2転換率やリピート購入率といった行動指標まで追うことが求められます。
● ツール導入=CRM運用だと誤解する
CRMツールを導入した時点で「CRMを始めた」と捉える企業も少なくありません。しかし、ツールはあくまで実行支援の手段であり、ツールが自動で戦略を考えてくれるわけではありません。
D2CにおけるCRMは、顧客との関係をどう設計するかという視点が起点にあります。ツール選定や導入の前に、どんな関係をどのフェーズで築くかというシナリオが存在しない限り、成果にはつながりません。
● 顧客を一枚岩で扱ってしまう
全顧客に対して同じアプローチを繰り返すと、反応は鈍くなっていきます。とくにD2Cでは、初回顧客、リピート顧客、休眠顧客で状態や心理がまったく異なります。
例えば、新商品リリース時に全顧客に同じ案内を送るのではなく、過去の購買傾向や接触頻度をもとにメッセージの内容やタイミングを調整すべきです。セグメントを設計しないまま配信すると、CRMは単なる情報通知になり、関係性の構築からは遠ざかってしまいます。
06|CRMを成功させるための組織設計と体制づくり
どれだけCRMの設計思想が優れていても、実行する組織と運用体制が伴っていなければ成果にはつながりません。特にD2Cビジネスにおいては、マーケティング、カスタマーサポート、物流、システムなど、複数の部門が密接に関わりながら一貫した顧客体験を届ける必要があります。この章では、CRMの仕組みを社内に根づかせるための体制とマネジメントのポイントを整理します。
● 部門を超えた「共通言語」が必要
CRMを実装するうえで最大の障壁となるのが、部門間のコミュニケーションのズレです。マーケティング部門が描いている理想の顧客体験と、現場で顧客対応をしているカスタマーサポートとの間で温度差があるケースは少なくありません。
このズレを埋めるためには、CRM施策の背景にある顧客の状態や感情の変化を、社内で共通言語として共有することが重要です。たとえば「このセグメントは初回購入から3週間経過し、次のアクションが迷子になっている状態」といった具合に、データだけでなく文脈まで共有することが、関係構築の精度を高めます。
● 「誰が責任を持つのか」を明確にする
CRMの設計と運用には、横断的な視点が欠かせません。しかし、実際の組織運営では「誰がリードを取るのか」が曖昧なまま進んでしまうことがあります。マーケティングが全体戦略を描いても、日々の配信や接点運用が各現場任せになると、徐々に一貫性が失われていきます。
そのため、CRMにおける「設計責任者」と「運用責任者」を明確にし、それぞれの役割分担と連携フローを設計する必要があります。また、PDCAを回すためのKPI設計とモニタリングの仕組みも欠かせません。
● 小さく始めて、成果を見せてから広げる
組織を巻き込むためには、いきなり全社導入を目指すのではなく、まずは一部のシナリオやセグメントに絞って小さく始めることが有効です。たとえば「初回購入から7日後のLINE配信でF2転換を促す」など、明確な目的とKPIを設定し、短期間で成果を出せる設計にすることで、社内の理解と協力を得やすくなります。
成果が可視化されれば、他部門への展開やシナリオの拡張もスムーズに進みます。CRMを「回る仕組み」にするには、成果を軸にした社内巻き込みが重要です。
D2Cビジネスにおいて、CRMは売上を左右する中核戦略です。mtc.では、ブランドと顧客のこれからの関係をどう設計すべきか?という問いに向き合う、無料のCRM構造診断を行っています。
- 今のCRM施策は、顧客の態度変容に応じた構造になっているか。
- 継続やファン化につながるコミュニケーション設計になっているか。
1つ1つの接点の「役割」から、全体設計を見直してみませんか?